強迫性障害の種類と症状や原因と治療法【診断基準は?】

強迫性障害の症状や治療と完治および再発や仕事について
強迫性障害は自分では気がついていない人が多い厄介な障害です。
いくつかの種類があるのですが、それぞれどのような症状なのでしょうか?
そして、原因や診断・治療方法はどのようなものなのでしょうか?
完治までの道筋や再発の確率といったものも気になる所かと思います。
本記事ではこの強迫性障害についてお伝えいたします。
強迫性障害とは?

強迫性障害とは精神障害の一種であり日常生活に支障が出てしまうほどの障害です。
皆さんが一度は気にしたことがある「玄関に鍵をかけたっけ?」とか「ガスの元栓は閉めたっけ?」といった不安が著しく強くなってしまい、何度も何度も家に戻って確認するような状態が強迫性障害になります。
このように日常生活を送る上では皆さんが感じたことがある不安やちょっとした恐怖があまりにも大きくなってしまうことで、体力や精神力がすり減ってしまう状態になるので、かなり厄介なのです。
ただし、「ちょっと神経質なだけ」とか「病気ではない」と考えている人が圧倒的に多いので障害と思われていないケースが多々あります。
何らかの強い不安は病気といった症状に繋がりやすいのですが、このような再確認的なものというのは病気と言うよりもその人の性格的なものという認識が強く、周りの人も気がつかないことがあります。
しかしながら日常生活に支障をもたらすようなものならば障害なのです。
世界保健機関も生活上の機能障害をひきおこす10大疾患の一つにしており世界規模の障害となっております。
種類と症状について
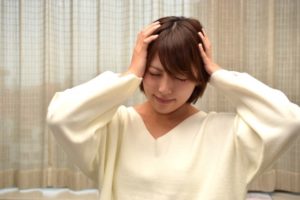 強迫性障害には強迫観念と強迫行為の2種類が存在します。
強迫性障害には強迫観念と強迫行為の2種類が存在します。
強迫観念とは頭からなかなか離れてくれない不安や恐怖や考えで、いつまでたってもつきまとってきます。
これが先ほど記載した「玄関に鍵をかけたっけ?」という類のものです。
そして、これらの強迫観念が強まってしまうとついに行動となってしまい、何度も何度も繰り返してしまう行為を強迫行為と言います。
代表的なケースをいくつか記載すると、例えば汚れや細菌やウイルスに対する強迫観念が強すぎることで衛生管理があまりにも度を超したものとなってしまい、手をひたすら洗うようになるとか、ずっと手袋をし続けるといった行為が当てはまるでしょう。
その他には、戸締りに関することでガス栓や電気器具のスイッチを切っかや鍵をかけたかなどが不安になって何度も確認するようになります。
数字やルーティンへのこだわりも圧倒的に強くなるというものもあり、自分にとって縁起が悪い数字は極端に避けるようになったり、決まったルーティンを行わないとその日1日の調子が整わなくなってしまったりというものがあります。
ただし、このルーティンや数字へのこだわりに関してはプロのスポーツ選手があえてこだわっているケースも多いのですが、障害かどうかは生活に支障が出ているかどうかになるでしょう。
原因について
 大脳基底核障害が強迫性障害の発症に関与しているとか、側頭葉・辺縁系が関与しているとか、前頭葉が関係しているとか何らかの脳のトラブルによって障害が出ているという説が有力です。
大脳基底核障害が強迫性障害の発症に関与しているとか、側頭葉・辺縁系が関与しているとか、前頭葉が関係しているとか何らかの脳のトラブルによって障害が出ているという説が有力です。
他にも心理的な要因から発症するとも言われています。
しかし、突発的に発症することも多く原因については謎に包まれているようです。
ただし、脳内のトラブルやセロトニンやドーパミンなど神経伝達物質に何らかのトラブルが発生すると強迫性障害が出やすいという報告がすでにあるので、ストレスフルな追い詰められる環境や生真面目で自分を追い込んでしまう性格な人ほど発症しやすいと言われております。
今まで発症していなかった人でも結婚や出産、身近な人の死といった大きすぎる転換期を迎えることで発症しやすくなるという報告もあるので、メンタル的に与える衝撃が大きいと出やすいといった傾向があるようです。
診断基準について
 これは国際的な精神疾患の診断基準が設けられているのでそれに基づきます。
これは国際的な精神疾患の診断基準が設けられているのでそれに基づきます。
具体的には「精神疾患の診断・統計マニュアル」第5版通称「DSM-5」を使うようです。
これはアメリカ精神医学会が設けた基準で強迫症/強迫性障害に関しても明確な基準を設けています。
では「Es Discovery」のウェブサイトから引用します。
A.強迫観念または強迫行為のどちらか、または両方が見られる:1と2によって定義される強迫観念。
1.反復的で持続的な思考・衝動、または心像であり、それは症状のある期間の一時期には、侵入的で望まないものとして体験されており、多くの人に強い不安や苦痛を引き起こすことがある。
2.その人は、この思考・衝動、または心像を無視したり、または何か他の思考または行為(強迫行為)によって中和したりしようと試みる。
1と2によって定義される強迫行為。
1.反復行動(例:手を洗う・確認する・順番に並べる)または心の中の行為(例:祈る・数を数える・心の中で言葉を繰り返す)であり、その人は強迫観念に反応して、または厳密に適用しなくてはならない規則に従って、それを行うように駆り立てられていると感じる。
2.その行動や心の中の行為は、不安または苦痛を予防したり緩和したり、または何か恐ろしい出来事や状況を避けることを目的としている。しかし、この行動や心の中の行為は、それによって中和したり予防したりしようとしている事とは現実的関連を持っていないし、または明らかに過剰である。注意:幼児・児童はこれらの行動や心の中の行為について十分な言語化による説明ができないことがある。
B.強迫観念または強迫行為は、時間を浪費させる(1日1時間以上かかる)、または臨床的に著明な苦痛を生じさせたり、社会的・職業的あるいはその他の重要な局面での機能を障害したりする。
C.強迫症状は、物質(例:乱用薬物・薬物)または他の身体疾患の生理学的作用によるものではない。
D.その症状は、他の精神障害の症状では上手く説明できない。
参考:強迫性障害・身体症状関連障害(DSM-5の診断基準):http://esdiscovery.jp/griffin/psycho01/dsm5_05.html
治療方法について
 主な治療法は薬によるものと行動によるものの併用です。
主な治療法は薬によるものと行動によるものの併用です。
薬による治療は抗うつ薬として用いられるセロトニン再取り込み阻害薬や三環系抗うつ薬を使ってメンタル的に安定した状態にすることであり、そこでメンタル的に安定させてから行動療法を行うようです。
行動療法のやり方は自ら強迫観念に逆らってもらうという単純な方法です。
鍵をかけたか本当に不安でしょうがないという人は、施錠確認で戻らないように我慢することになりますし、とにかく手の汚れが気になって仕方が無いという方は一回の手洗いが終わったらそれ以上洗わないよう我慢してもらいます。
完治する?
 メンタルな病に近いので、完治の定義が難しく100%再発することなく気にしないで生活できる状況に持って行けるかどうかとなるとはっきりとは言えないでしょう。
メンタルな病に近いので、完治の定義が難しく100%再発することなく気にしないで生活できる状況に持って行けるかどうかとなるとはっきりとは言えないでしょう。
ただし、昔よりは精神的な病気に対する対策も整っているのでかなりのレベルまで治るようになったようです。
完全な状態になるのは難しくても日常生活を送る上ではほとんど問題ないくらいは復帰できる可能性は十分あると考えて良いでしょう。
ただ現状、精神的なケアや薬物療法、漢方薬を使った治療や脳神経外科治療や脳深部刺激療法などいろいろな方法がありますが、まだまだ研究は続いている最中なのです。
再発について
 メンタル的な病気はかなり再発率が高く、この強迫性障害も例外ではありませんでした。
メンタル的な病気はかなり再発率が高く、この強迫性障害も例外ではありませんでした。
元々提案されていた薬による治療法だけでは再発率がかなり高かったとのことですが、薬と一緒に行動療法を続けて治療してもらうと予後はかなりよくなるようです。
もともと、この強迫性障害は完治を目指すのではなく日常生活に支障をきたさない程度には改善した「寛解(かんかい)状態」を目指しますので、そこが到達地点なのです。
今の治療法である行動療法をしっかりとこなせばおよそ60~90%の改善率と言われており、かなり良くなったようです。
仕事について
 メンタル的な病気になってしまうと仕事をするのがなかなか大変な状況になってしまいますが、精神科での日帰りリハビリテーションなどもありますので、まずはしっかりと完治させることが重要です。
メンタル的な病気になってしまうと仕事をするのがなかなか大変な状況になってしまいますが、精神科での日帰りリハビリテーションなどもありますので、まずはしっかりと完治させることが重要です。
仮に就職できないという人でも就労が可能な人に働く場を提供するための支援を行う就労継続支援事業所を使うという方法もあります。
また就労移行支援サービスもあるのでそちらを受けるという方法もあります。
強迫性障害につきましては、次のサイトも参考にしてみて下さい。
最後に
以上、いかがだったでしょうか?
本記事では強迫性障害について記載いたしました。
この強迫性障害というのはいわゆる潔癖症と呼ばれるような人たちや、プロのスポーツ選手のように試合のある日や登板する日に行う勝利の儀式といった行動も含まれます。
これを病気かどうかと判断するのは自分ではなく医師なのでしょうが、本人も周りの人たちも日常生活に大きな支障が出ていないレベル大丈夫ということになるかと思います。


LEAVE A REPLY