梅毒の感染率や潜伏期間と症状や検査法!治療法と薬について

男性・女性の梅毒の症状や感染経路および完治するのか?
梅毒は現代日本でも猛威を振るっており、感染率も落ちていないと言われております。
この梅毒の潜伏期間や症状、検査方法はいったいどのようなものなのか、治療法はやはり薬が中心なのかと気になる部分がいろいろとあるでしょう。
本記事ではこの梅毒の感染率や潜伏期間および症状や検査・治療を中心にお伝えしたいと思います。
梅毒の感染率は?

一回の性行為で感染する確率は15~30%と言われており、かなり高いといえるでしょう。
性病の中でも感染率は高い方といえます。
基本的な感染経路が性的接触にあることから、若い世代に圧倒的に多くなっております。
平成22年~27年までの5年間で発症者が4倍にまで膨れ上がり、発症している女性の76%が15~35歳の女性とのことです。
潜伏期間について
 梅毒の潜伏期間はだいたい3週間と言われております。
梅毒の潜伏期間はだいたい3週間と言われております。
ただし、これはあくまで目安ですので、感染したのかもしれないと感じたのなら潜伏期間中のうちに病院で検査をした方がいいでしょう。
潜伏期間とは病原体に感染してから症状が出るまでの期間なのですが、当然症状が出るまでの間も病原体を持っています。
つまり、初期段階の症状が出る前から梅毒になってるので気が付かないうちに人にうつしてしまう可能性があるということになります。
症状について
 梅毒は段階によって第1期から第4期まで分かれており、それぞれ症状が異なります。
梅毒は段階によって第1期から第4期まで分かれており、それぞれ症状が異なります。
第1期は初期症状と言われており、第4期は末期症状として考えられているようです。
まず第1期の症状は感染した箇所の皮膚か粘膜に5~20ミリぐらいの硬いしこりができます。
しこりは出来るのですが、痛みはありません。
リンパの腫れといった症状も出るでしょう。
男性の場合は男性器にこのしこりができるのでこの段階で高確率で気が付きます。
しかし、女性の場合は性器内部にできるので気が付かない方が多いです。
第2期になると梅毒が血液やリンパの流れで移動をするので体全体に症状が出ます。
具体的には顔や首や背中などの全身に赤色の発疹がでるバラ疹やそのバラ疹を小さくしたような赤褐色の梅毒性丘疹、頭皮にイボができることで発生する脱毛など色々とあるのです。
他には関節痛・腎炎・頭痛・倦怠感・発熱などの症状も出る場合があります。
第3期になるとゴム腫というゴムのような腫瘍が全身にできます。
これは肝臓や腎臓といった内臓器官や骨や筋肉にもできるようになるので、非常に危険です。
第4期はもはや末期といっていいでしょう。
歩行障害や大動脈瘤などの症状が出て脳のダメージも深刻になるので脳障害になってしまうことすらあります。
検査方法について
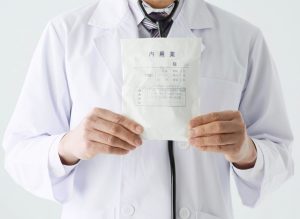 梅毒の検査方法としてメジャーになっているのはSTSとTP抗原法です。
梅毒の検査方法としてメジャーになっているのはSTSとTP抗原法です。
その両者の考え方は基本的に同じで、梅毒トレポネーマに対する抗体がどれだけできているのかを調べる方法となっております。
まずSTS法はserologic test for syphilisの略で、梅毒トレポネーマが体内で暴れて細胞を壊して出てきたリン脂質のカルジオリピンに対する抗体の数を調べます。
いわゆる自己抗体というものなのですが、梅毒に感染して2~5週間後であれば使うことができる検査方法なので、初期症状の段階で調べるのに使われているのです。
もう一つのTP抗原法は梅毒トレポネーマに対抗するために出てきた抗体の数を調べる方法であり、STS法よりも制度が高いと言われております。
しかし、この抗体は感染してから3ヶ月程度経過しないと出てこないとのことですので、早期検査には使えません。
基本的にこの2つの検査を同時に行って感染しているのかどうかを調べることになります。
治療方法と薬の種類
 梅毒の治療の基本は投薬治療で、使う薬はペニシリン系の抗生物質が基本です。
梅毒の治療の基本は投薬治療で、使う薬はペニシリン系の抗生物質が基本です。
このペニシリン系の薬は非常に種類が豊富ですが、主に使われるのは「サワシリン」「パセトシン」「ノバモックス」あたりでしょう。
サワシリンは咽頭炎や気管支炎などの病気にも使われますが殺菌作用が強く梅毒トレポネーマにも有効なのです。
パセトシンも殺菌作用が強くペニシリン系の薬としてよく使われております。
ノバモックスだけがちょっと特殊でサワシリンのジェネリック医薬品ですがサワシリンと使い方は一緒なので特段気にする必要はないでしょう。
妊婦が発症していた場合はアセチルスピラマイシンを1日200㎎、6回に分けて投与するというやり方の他、同じくペニシリン系の薬を使うというやり方になるようです。
ただし、一部の人たちはペニシリン系の薬に対してアレルギー症状が出てしまう恐れがありますので、その場合には塩酸ミノサイクリンやエリスロマイシンなどの別の薬を使うことになるでしょう。
梅毒の原因や感染経路
 梅毒は性感染症の一つであり基本は性交によって感染します。
梅毒は性感染症の一つであり基本は性交によって感染します。
感染力もかなり強くオーラルセックスやアナルセックスでも喉や直腸に感染する恐れがあるのです。
粘膜接触で感染するので、キスだけでもうつることすらあります。
また、母子感染もありますので、梅毒にかかっている女性が妊娠した場合、そのまま治療せずに子供が生まれた場合、その子供が梅毒になってしまうこともあるでしょう。
生まれたばかりの赤ちゃんが梅毒になっている場合は「先天性梅毒」と呼びます。
現代日本では妊娠初期の段階で病院の方で梅毒などの性病に感染していないのかをチェックするので、母子感染の数も減ってきています。
それ以外では輸血や傷口同士の接触で感染することもあるのです。
これは血液感染と言われておりますが、この感染経路も現代日本ではほとんど発生していないようです。
完治する?
 梅毒は感染して2年以内であれば、ほとんどの確率で完治する病気と言われております。
梅毒は感染して2年以内であれば、ほとんどの確率で完治する病気と言われております。
第〇期というような時期で考えると、第2期の半ばまでに治療を開始すれば完治するという考えになります。
逆に言えば症状が進行して第2期後半~第4期にまで悪化してしまった場合は完治するのかどうか分からなくなると言えそうです。
基本的にこの梅毒は第1期までは分かりにくく気が付きにくいのですが、第2期は特徴的な症状がいくつも出てくるので気が付かない人はいません。
気付いた段階で必ずすぐに治療を開始してください。
また、免疫力次第で治療速度や回復するか否かも大きく変わってきますので、規則正しい日常生活を送る必要があります。
しっかり食事をして、運動を行い、睡眠をとりましょう。
感染率など梅毒につきましては、次のサイトも参考にしてみて下さい。
一般社団法人 日本感染症学会 https://www.kansensho.or.jp/ref/d52.html
最後に
以上、いかがだったでしょうか?
本記事では梅毒の感染率や治療方法などを記載してまいりました。
梅毒は発症する人が現代になって増え続けている性病の一つで、何気にインターネット上でも調べている人の数が増えているワードになっております。
しかし、治療するための薬は病院で診察を受けないと入手できないものとなっておりますので、発症したという疑いがあるのでしたら、検査を受けて治療薬をもらうようにして下さい。
放置していても悪化するだけで治るものではありません。
必ず、梅毒に気が付いたのなら医師に検査してもらって診てもらい、薬を処方してもらいましょう。


LEAVE A REPLY