梅毒の感染経路【風呂・プール・血液・唾液・介護・トイレ】
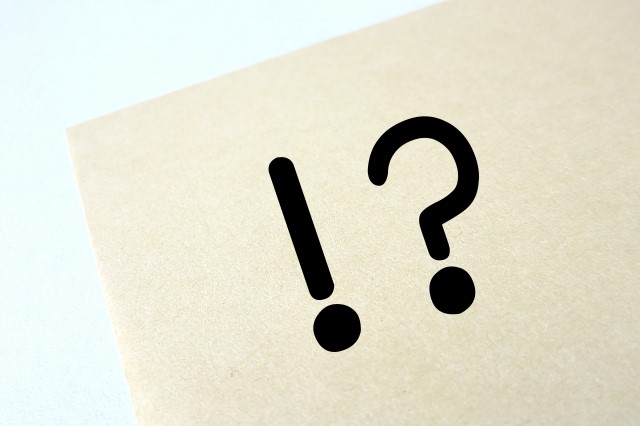
温泉やキス・針刺し・母子など性行為以外の梅毒の感染経路
梅毒は恐ろしい性病の一つですが、きちんとした対応をすれば治ります。
そんな梅毒の感染経路に成功以外において風呂・血液・唾液・介護・トイレ・プール等でもうつるとかうつらないとか言う話があります。
本記事ではこの梅毒の感染経路について調べていきたいと思います。
梅毒の感染経路で最も多いのは性行為
 一般的に梅毒は性感染症の一つなので、性行為関連でうつる可能性が最も高いと言われております。
一般的に梅毒は性感染症の一つなので、性行為関連でうつる可能性が最も高いと言われております。
いわゆる粘膜感染が主体ですので、性行為やキスといった粘膜接触が多い行為が多いと感染する確率が高まるのです。
男性の場合の梅毒の症状は特殊なできもののようなものができると言うことなので、分かりやすいのですが、女性の場合は性器の中でできてしまうようになるので初期症状に気がつかないでパートナーにうつしてしまう可能性があるのです。
梅毒は梅毒トレポネーマという病原体の一種である細菌が体内に侵入することで、感染した部位にしこりや腫瘍を作るという特徴がありますが、何と言ってもやっかいなのが一度感染したら2度と感染しなくなる終生免疫ができない病気なので、人によっては何度も発症します。
しかし、この性行為以外の行動でもうつる可能性があると言うことをご存じない方も多いかと思いますので、ここではそれ以外の部分を探っていきます。
梅毒の感染経路で性行為以外は?
性行為以外の感染経路においては日常生活で当たり前のように行っている行動でもうつってしまうことがあるのでしょうか?
日常的において気になる感染経路について記載します。
お風呂・温泉・プール
 お風呂や温泉、プールといった施設は多くの方々が利用する大規模施設になるため、そこで感染してしまう場合は集団感染となってしまい瞬く間に梅毒感染者が広がってしまうでしょう。
お風呂や温泉、プールといった施設は多くの方々が利用する大規模施設になるため、そこで感染してしまう場合は集団感染となってしまい瞬く間に梅毒感染者が広がってしまうでしょう。
しかしながら結論から言ってお風呂やプールや温泉程度の間接的な粘膜接触程度では感染する確率はほとんど無いと言えるでしょう。
ウイルスは知能が無くただ浮遊するだけで傷口を探すという特性が無く、さらに梅毒のウイルスは体外に出るとかなりの速度で弱り感染力が落ちるのでうつることは無いと考えられているのです。
血液
 感染経路として輸血等の血液感染は可能性があります。
感染経路として輸血等の血液感染は可能性があります。
感染者からの臓器提供や血液の提供があった場合、または感染者と傷口同士がふれあうといった接触があった場合は感染する可能性があります。
それでも、日常生活において両者の傷口同士が触れ合うということは、なかなか無いので輸血などが無い限りはうつらないと考えてもいいでしょう。
キスなど唾液
 これは可能性があると言えるでしょう。
これは可能性があると言えるでしょう。
梅毒の原因となる病原体が口の中にも感染することがあるため、うつる可能性はあると考えられています。
HIVはキスでは感染しないと言われておりますが、梅毒は感染すると言うことを覚えておきましょう。
介護
 介護に関しましては日常的な接触をしていたとしても感染することはありません。
介護に関しましては日常的な接触をしていたとしても感染することはありません。
介護老人保健施設等で梅毒の老人が入院したとしても梅毒をまき散らす可能性は低いのです。
梅毒検査で陽性が出てしまった高齢者がどれほどの感染力を持っているのかは不明ではありますが、何れにしましてもそこまで心配する必要は無いようです。
トイレ
 性感染症の一つと言うことでトイレも何となく怖いと感じるかもしれませんが、病原菌の梅毒トレポネーマは乾燥や低温に弱く低酸素状態の体液内でしか生存できないという特性があるため、トイレが感染経路になる可能性はほとんどありません。
性感染症の一つと言うことでトイレも何となく怖いと感じるかもしれませんが、病原菌の梅毒トレポネーマは乾燥や低温に弱く低酸素状態の体液内でしか生存できないという特性があるため、トイレが感染経路になる可能性はほとんどありません。
仮に便座カバーなどに付着してしまったとしても自動的に死滅すると考えた方がいいでしょう。
針刺し事故
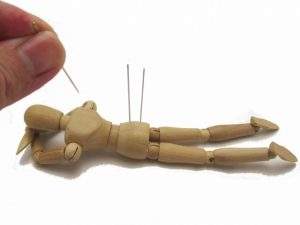 欧米の感染症の教科書のいくつかには梅毒患者の血液の針刺しにより感染が発生するという記載があるようです。
欧米の感染症の教科書のいくつかには梅毒患者の血液の針刺しにより感染が発生するという記載があるようです。
しかし、日本の医師の見解では血液暴露のガイドラインには梅毒への対応方法が記載しておらず、それらの可能性は低いと考えられております。
母子感染
 これは子供と親が粘膜的な接触をしたというものではなく、妊娠した女性が実は梅毒に感染していたため、生まれてきた子供が梅毒にかかってしまうというケースです。
これは子供と親が粘膜的な接触をしたというものではなく、妊娠した女性が実は梅毒に感染していたため、生まれてきた子供が梅毒にかかってしまうというケースです。
このような感染を母子感染と呼び、胎児の梅毒を「先天性梅毒」と呼んでおります。
少しだけ記載しましたが、男性の場合、性器感染で発症したのなら男性の性器にしこりや腫瘍がはっきりと初期症状として現れるので、初期段階でも簡単に気がつけますが、女性の場合これらのしこりや腫瘍が性器内にできてしまうので、初期症状にはかなり気がつきにくいのです。
そのため、一部の方はそのまま妊娠をして放置してしまう可能性があります。
このように記載はしましたが、現代医療では妊娠初期の段階で梅毒になっていないかをチェックするようになっており、義務化もされつつあるので母子感染は日本国内でもほとんど見られなくなりました。
感染者数の推移は?
 昔はかなり多くの発症者がいましたが、いろいろと予防法などの情報が拡散するようになってからは発症者も一気に低下して、ずっと感染者数は総数でも1000人を下回っておりました。
昔はかなり多くの発症者がいましたが、いろいろと予防法などの情報が拡散するようになってからは発症者も一気に低下して、ずっと感染者数は総数でも1000人を下回っておりました。
しかし、2011年以降急激に発症者が増えており、2016年のデータでは2010年と比べると7~8倍程度にまで膨れ上がっています。
2010年の報告数が621人、2013年は1228人、1016年は4518人となっています。
2017年はさらに増え5770人となっています。
その内訳もなかなかに特徴的で、男性患者の70%が30歳以上であり、女性患者の60%が29歳以下となっております。
男性はある程度年齢を重ねた人の方が発症しており、女性は若いうちに発症している割合が高いということです。
増えてきている理由はいろいろと考察が重ねられていますが、その一つが梅毒が医療技術の進化によって怖い病気ではなくなり、警告を発信する人たちが減ってしまったこともあるでしょう。
すでに、昔の病気として全く気にしないという方も増えてしまったことで、発症してしまった人が梅毒だと気が付かずに放置して拡散している可能性があるということです。
また、一説には外国人観光客への性サービス業を行なっている女性が日本にはかなり存在していると言われており、外国の方々からもらっているのではないのかとも推測されております。
日本では発症者数は非常に少ないですが外国ではそこまで対策をしておらず、発症者数が著しく多い国もありますので、そこから流れてくるケースを抑えることができていません。
予防法について
 梅毒の感染経路は母子感染・性的接触・血液感染の3つが主体なので、それらに気をつけるようにすれば感染確率はグッと減ります。
梅毒の感染経路は母子感染・性的接触・血液感染の3つが主体なので、それらに気をつけるようにすれば感染確率はグッと減ります。
特に、梅毒は性感染症と呼ばれているだけあって、一番多いのは性行為での感染になっております。
オーラルセックスや肛門性交でも感染しますし、口に病変が既にできてしまっている方とキスをしてしまった場合でも感染してしまうでしょう。
それらの感染防止のためにもコンドームの着用がある程度は有効ではありますが、口に病変がありキスなどで感染してしまった場合はコンドームでも防ぐことはできないので100%万能というものではありません。
つまり、不特定多数との性行為を避けるのが最もリスク回避としては得策になると言うことです。
もしかしたら感染してしまったかもしれないと思った時は、すぐにでも検査をした方がいいでしょう。
梅毒は放置して治るものではなく放置することでずっと悪化し続けて最後には死に至ってしまう病気ですが、初期段階で治療を受ければほとんど何事も無く治すことができるのです。
解決方法としては、不特定多数との性行為は避けて、性行為をするときはコンドームを着用し、怪しいと思ったら検査を受けると言うことになります。
梅毒は感染後すぐに症状が出るというものではなく、3週間ほど潜伏するとも言われております。
潜伏期間中にもうつるかどうかという議論がたまにされますが、症状が出ていなくても感染しているのであれば、その菌は体内に保有していることになるので、うつる可能性が出てしまうと言うことも忘れないで下さいね。
梅毒につきましては次のページも参考にして下さい。
梅毒の完治までの期間の目安と完治後の妊娠・出産時の子供への影響
梅毒の感染経路につきましては、次のサイトも参考にしてみて下さい。
STD研究所 梅毒の解説【症状や感染経路・検査や治療について】
最後に
以上、いかがだったでしょうか?
本記事では梅毒の感染経路について触れさせていただきました。
梅毒は基本的に3つの決まった方法でしか感染することはありません。
そのため、プールやトイレ、そして温泉といったものでは感染することがほとんどないと考えられているのです。
それでも100%無いとは言い切れないようなので、梅毒であるということが発覚したのならできる限り行動を制限して、治療を済ませるようにしてください。


LEAVE A REPLY